ここでは、スピーカを駆動するのに必要なパワーアンプの性能について検討します。
0、最低限度のレベル(必要条件のミニマム)
「最低限度は?」と聞かれると、「それに対する答えはない」と言うしかありません。
何故なら、人間の聴覚や音楽を感じる脳の働きは、その人の持っている記憶(想像力)によって補正され、どんなにノイズや歪みがあっても、音量が小さくても、周波数特性のバランスが崩れていても、「本来はこう演奏されているはずだ」と頭の中で補正して聞こうとするからです。
この補正する力は元の音楽や演奏を良く知っている人ほど大きく、例えば音楽の演奏家などは本格的なオーディオ装置は必要とせず、小さなラジカセで十分などと言う話は良く聞きます。
どんなプアな音でも本来の音をイメージするには十分であり、中途半端なリアリティは却って邪魔なのでしょう。
AMラジオから流れる懐かしい音楽に感動して涙する、という経験を持っている人も多いでしょうし、人を感動させる力とオーディオ装置の性能値は必ずしも比例関係にはありません。
それはそれとして、「Hi-Fi」と呼べる最低限度は存在すると仮定しても、歪み率、周波数特性、ノイズレベル、最大音圧レベルのどれを取っても一概に「ここまで」と線引きをするのは困難です。(明らかに本来の音と異なるのが分かるレベルを「必要条件」と定義したとして、これを満たさなくても音楽を鑑賞するのに本質的に支障はない場合も多い。)
したがって、ここで検討するのは聴覚限度により「違いが全く知覚できない」レベルを基準として、「これ以上の高性能化は聴感上で無意味」と言える十分条件を主に議論します。
【注】ここで定義した「十分条件」を満たした数値を持つアンプでも、「音質」が十分かは全く保証されないことに注意。数値が十分でないアンプは、その部分が「耳に聞こえる」可能性はあるが、不十分な特性が聞こえたとしても「音質」を汚しているかは別問題。
測定器で検出できる「歪み率」や「周波数特性」は、聴覚の検出限度をはるかに超えた性能を持つが、この値が「音質」を測る尺度でない事は昔から知られている。
1、聴覚限度との対比(十分条件)と、現実的に許容できる範囲(必要条件)
●ノイズレベル(残留雑音とS/N)
単純に「耳に届くノイズの音圧が0dBSPL以下なら聞こえない」と決めます。「サブリミナルな効果があるかも知れない」という疑問も残りますが、全く聞こえないなら違いは知覚できないと考えても誤りではないでしょう。
SPKからの音圧は距離に反比例し、一般的なリスニングポジションは1mより離れている為に直接音はSPKの能率値より低下しますが、部屋の反射で平均音圧が上昇する分を加味し、SPKの能率(dB/W)その物を変換ゲインとします。
1kHz付近の単音の場合は、SPKの能率を90dB/W、定格インピーダンスを8Ωとすると1Wは2.83V=+9dBVですので、アンプ出力が-81dBV=0.089mVrmsから聞こえることになりますが、熱雑音などの広帯域ノイズではバンド幅当りの密度により限度が変化します。
耳の最も感度の良い数kHzでの聴覚の臨界帯域は500~1kHz程度ですので、聴感補正のIHF-Aカーブ(BW=10kHz程度)を入れて測定する場合は、BW分を加味して0.2mV(2μV/√Hzの雑音電圧密度)なら聞こえません。
【結果】:90dB/Wの能率の8ΩSPKでは、聴感補正のIHF-Aカーブで0.2mV以下なら十分。
この値はSPKの能率に依存するので、110dB/Wのホーンドライバを駆動するアンプはAカーブ補正で0.02mV以下、100dB/Wの高能率ユニットでは0.06mV以下のノイズレベルである必要があります。
実際の生活空間では常時20~30dBの暗騒音がありますから、この値より20dB悪くても実用上はさほど問題とはなりません。(耳を澄ますとサーと聞こえても、音楽が鳴っていれば気にならない)
但し、pppになった時の静寂感などで差が出ますので、1mV以下が望ましい。(必要条件)
●歪み率
歪みの知覚限度は音圧の限度とは違って測定が難しく、明確なデータは揃っていません。
書物で見られるデータでは「マスキング限界」が参考になりますが、一番知りたい2次、3次高調波の検知限度は、その付近に発生する耳内倍音との唸り音を聞いてしまうためカーブはうねっており、非常に非線型な特性を示します。(例えば、こちらのデータなど。)
ビートの発生しない「狭帯域ノイズ」とのマスキングを評価したグラフ(J.P.Egan and H.W.Hake/1950)から、400Hzで80dBSPL音が与えるマスキング限界を読み取ると、
2次歪み( 800Hz):37dBSPL → 0.7% まで
3次歪み(1.2kHz):26dBSPL → 0.2% まで
5次歪み(2.0kHz):12dBSPL → 0.04%まで
であり、この値が一般的な歪みの検知限界(必要条件)と言えそうです。
良く言われる「真空管シングルアンプの2次歪みは有害ではない」と言うのは、この数字を見るとあながち嘘ではない事が分かります。トランジスタアンプのクロスオーバー歪みは高次の成分が多いので、3次歪みも含めての値で0.1%以下が必要。
これは「混入した音が聞こえたか」のデータであり、歪み成分の音圧が0dBSPLを超えていれば何らかのニュアンスの違いとして変化を感じる可能性はある訳で、厳しい基準としては音圧80dBでも歪み成分が0dBを超えない値=0.01%以下であれば十分と言えるでしょう。
【結果】:音圧80dB相当出力(0.1W=約1.0V)に於てTHD=0.01%以下なら十分。
なお、音圧がさらに大きくなれば同じ歪み率でも歪み成分は0dBSPLを超えてきますが、耳の非直線性で音圧が大きいほど耳内倍音が増加し、マスキング限界は加速度的に上昇しますので、10V出力(10W程度)では率で0.1%程度でも全く問題ないと思われます。
実際に、音圧100dB単音の場合のマスキング限界は5次の周波数でも70dBSPLに達し、大音量では3%程度までの歪みはマスクされやすい性質を持ちます。(近年ではイヤホンで大音量で音楽を聴く若い人向けに聴感上の音量を上げたクリップしまくりのひどい歪の音楽ソースが主流となっていますが、100dBSPLを超える大音量では歪は10%あっても聞こえにくいので、「音がでかい方が迫力がある」のが好まれるのです。)
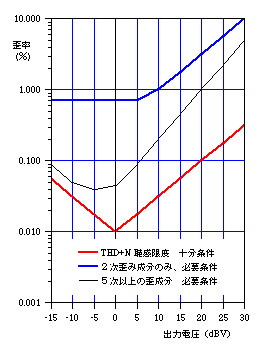
以上の結果をグラフで表したのが右図です。(SPKの能率が90dB/Wの場合。8Ωの場合は+30dBVで125W出力。)
下の右肩下がりの直線部はTHD+Nのノイズ成分、
上の水平のラインはマスキング限界の数値、
右肩上りの部分は耳の非直線性によるもの。
高次の歪み成分は小出力時ではマスキングされにくいので、普通に分かってしまうレベル(必要条件)が聴覚限度(十分条件)に近付いています。
市販アンプの定格歪み表示値は、定格出力時で0.1%程度が多いですが、実力値で十分条件を外れることはまずありません。
歪み率の値に関しては、デジタルアンプ(残留ノイズが多く、小出力時の歪み率も0.01%まで下がらない事が多い)以外は気にしなくて良いでしょう。
半導体アンプであれば-3dBのカットオフ周波数を2Hz~200kHz以上に広げることは難しくないので、余程のことがなければ可聴帯域である20Hz~20kHzに影響することはまずありません。
1次のカットオフであれば、fcを再生帯域の5倍以上:4Hz~100kHz:に設定すれば、減衰量は0.1dB程度で済み、耳では違いは感じられません。(十分条件)
実用上では、低域は30Hzで-1.0dBとなるfc=15Hz、高域は10kHzで-0.5dBとなるfc=30kHz程度が必要条件となり、これより帯域が狭いと聴感上で明らかな変化が感じられるようになります。
現実的には、CDプレーヤーの出力コンデンサの値など、計算上のカットオフを5Hzから2Hzまで下げる(コンデンサの容量を大きくする)と、50Hzまでしか再生出来ないSPKで聴いても、ぐっと低域が力強くなったりしますが、これは周波数特性が変化したのではなくて帯域内の音の出方が変化するためで別の原因です。
出力トランスを持った真空管アンプ等では、低域、高域共に2次以上の急な減衰カーブになりがちで、その場合は少し様子が異なります。
可聴範囲の近くにピークやディップ(急な位相変化)があると音色に変化を及ぼすので、出来れば100kHz以上にして、ダンピングのCR等でなるべくブロードな変化に抑えたいところ。聴覚の研究データでは高域の位相は検知できない事になっていますが、位相その物が問題なのではなく、その原因によって音色の変化を生じている気がします。
帯域内のフラットネス(ピークやディップ)も基本的には同様で、±0.1dB以下なら聞き取ることは出来ず、±0.5dBを超えると明らかな変化が感じられるようになりますが、これは単に周波数特性のレベルだけの話で、音質的なバランスはF特だけでは測れません。
やっかいなのは、「質」による帯域バランスの崩れを「量」で多少なりとも補正できてしまう事で、質の悪い耳に付く帯域をF特をいじって量を下げれば全体のバランスは良くなった気がしますが、本質的には何も改善されません。
測定器を用いないで、聴感のみでマルチアンプシステムのバランスを取ろうとするとこの罠に陥りやすく、物理的なF特フラットからスタートして、聴感上気になる部分を対策していく方が良い結果を得られます。
【参考】イコライザによる周波数特性の補正
スピーカや部屋の定在波による周波数特性の乱れをグラフィックイコライザで補正する事も良くあります。
完全に位相特性も含めて打消しが出来れば良いのですが、それにはデジタル的に伝達関数を測定して、その逆特性をデジタル的にプログラミングする必要があり、アナログで「擬似的」に補正するのは十分な効果はありません。(スピーカや部屋の機械的な共振Qはかなり高く、狭い周波数範囲で共振点とQを合わせないと打ち消せない)
さらに、座る位置が数cmずれるだけでその伝達関数もころころ変わってしまうので、室内空間での再生では逆関数での打消しは実用的ではない。
Qやfoが固定のグラフィックイコライザで補正出来るのは、ブロードな変化を「大雑把に」合わせる所までなので、その程度の効果であれば期待できます。(イコライザを追加することによる劣化と、帯域バランス改善のどちらを取るかの選択)
●出力インピーダンス(ダンピングファクタ)
これは、組み合わせるSPKとの相性で必ずしも値が大きいほど良いとは限らない所が難しいですが、
・出力インピーダンスが大きいと、アンプ出力電圧そのものが負荷の変動に影響される
・アンプの出力インピーダンスによりSPKの特性(特に低域のダンピング)が変化する
の2つの点を考慮しなければなりません。
低域を豊かにゆったり鳴らす方が好ましいバランスのSPKなら、DFの値が10以下のアンプが好結果を得る事も多いですが、普通は電圧駆動のアンプを前提として設計されたSPKが多いので「必要にして十分なDFの値」を検討します。
負荷インピーダンス変化によるアンプ出力電圧の変動を0.1dB以下とするにはDF>100であれば良く、これが「十分条件」となります。
±0.5dB以下とするにはDF>20が必要で、電圧駆動のアンプとしてはこれが必要条件となるでしょう。DF=10程度のアンプは「ダンピングの甘い」アンプという事です。
一方、SPKを制動する為の条件は、SPK自身の電磁制動力の低化を5%以下に抑えるにはDF>20が必要。
DFの値が100→1000になったとしても、電磁制動力の変化は0.9%に過ぎませんし、接続するケーブル(SPKシステムの内部配線も含む)の抵抗分が往復で20mΩなら、4ΩのSPKではアンプのDF=1000でも結果的にDF=167にしかならないので、100を超えるDFの値ならそれ以上はあまり意味がありません。
(現実的には、ボイスコイル自身の温度上昇による抵抗値増加の方がもっと影響が大きい)
●最大出力電圧、電流
出力電圧は定格出力に依存するので対象外とし、必要な最大電流を検討します。
抵抗負荷の場合はピーク出力電流は、Iop=√(2P/R)で、100W/4Ωの場合は7.1Aとなり、中域以上のユニットではこの値に余裕率を加味した値(10A程度)まで供給できれば問題ありません。
低域を受け持つユニットの場合は少し様子が異なり、ボイスコイルの起電力の影響を考慮する必要があります。
一般的にはインピーダンス特性の最も低下する、バスレフの共振周波数の谷の値(B&Wの800Dでは3Ω)で考える人が多いのですが、実はその上のインピーダンスが高い部分(ユニットのfoの山)が最も厳しいのです。
何故かというと、インピーダンスが上昇しているfoの山は、ボイスコイルの運動速度が最大となる周波数であり、「逆起電力」によって電流が流れにくくなっているためにインピーダンスが見かけ上高く出ます。
では、20Vrmsの電圧を印加してボイスコイルの逆起電力が同じく20Vrmsとなっている瞬間に印加電圧が逆極性に反転したらどうなるか。
逆起電力のピーク値28.3Vに逆極性の駆動電圧28.3Vピークが加算されますから、ボイスコイルの直流抵抗が3Ωなら瞬間的に18.9Aもの電流が流れる計算です。
バスレフ共振周波数の谷では、振動板(ボイスコイル)は動いていないので逆起電力の発生もなく、最大ピーク電流はその半分にしかなりません。
この事から、2種類の条件(8Ωの中域以上ユニットのピーク×1.4倍、DCR=3Ωウーハーの理論最大ピーク)について定格出力値別に最大出力電流を計算すると、
| 8Ω定格出力値 | 8Ω高域ユニット ×1.4倍余裕率 | DCR=3Ωウーハー 理論最大ピーク |
| 5W | 1.6A | 6.0A |
| 10W | 2.2A | 8.4A |
| 25W | 3.5A | 13.3A |
| 50W | 5.0A | 18.9A |
| 100W | 7.1A | 26.6A |
| 200W | 10.0A | 37.7A |
8Ω25Wという小出力のアンプでも、つなぐSPKによっては瞬間的に10Aを軽く超える電流を必要とすることが分かります。「1Ω負荷でも大丈夫」がセールスポイントのアンプもありますが、一概に無駄とも言えません。
バイポーラTrの出力段では、出力石の最大定格の40-50%電流が直線性の良い範囲ですから、40A近い最大電流供給能力を得るには、10Aクラスの石なら8個は並列接続が必要となります。
高級アンプでは出力石に10個以上の並列接続をしているのもありますが、これは「どんな負荷を繋いでも壊れない」のが主目的です。(ハイパワーアンプでは出力Trに高電圧が掛かるが、バイポーラTrは高圧では極端に許容電流が減るのでASOの余裕を見ると必要な並列数が多くなってしまう。)但し、結果的に電流供給能力の余裕が生まれて好結果を招いている側面もある。
一方、8Ω50W程度の小出力では10Aクラスの石が1個で定格負荷には十分ですが、駆動するSPKによっては電流の直線性を考慮すると10Aクラスの石で4パラが望ましい。一般的にはここまで本格的なパワー段を備える小出力アンプはあまりなく、「”駆動力”はハイパワーアンプでないとダメだ!」という神話はこうした事が原因なのかも知れません。
(これは、8Ω表示なのにウーハーのインピーダンスが3Ωという特殊なSPKの場合の話で、普通の6ΩSPKであればこの半分の電流供給能力でOK。)
なお、SPKのインピーダンス変動と逆特性のLCR共振回路を接続して、インピーダンスを平坦にする手法があります。これで低域共振のピークをつぶすと電力的には非常にロスが大きいのですが、「逆起電力」による最大ピーク電流の増加は抑えられる(アンプからは抵抗性に見える)ので、アンプにとっては良い対策です。
2、システム総合でのノイズ特性の計算
●ソース源(音量VR前段階)の残留ノイズとDレンジ
どんなに元のS/Nが良くても、ゲインをどんどん上げてSPKに耳をくっつければ最後はノイズが聞こえるわけですが、音楽を聴かないでノイズだけ聞いても意味がないので、実使用状態の最大ゲインで考えます。
「アンプに必要な出力について」の所で検討したように、実使用状態の最大ゲインはシステムの最大音圧出力で決まり、ソースの定格最大出力(0dB)で110dBSPL程度が防音された室内での通常の最大レベルと考えられます。
(音圧ピーク100dBですぐ横の人と会話が困難なレベル、110dBでは壁や床と共に部屋全体が揺れるレベル。これ以上のゲインを持つシステムであっても、実使用状態ではこれ以上に音量を上げることはほとんどない)
従って、ソースのDレンジ(残留ノイズと最大出力レベルの比)が110dBあれば最大VR時でも耳には聞こえません。元の録音レベルが低い場合はその分音量を上げる事もあり、ゲイン設定その物はさらに6dB程度余裕を取りたいのでこの場合残留雑音は+6dBSPLになりますが、広帯域のノイズなら実害はありません。
0dBを2.0Vrmsとした場合、抵抗の熱雑音でAカーブ補正で-110dB(6.3μV)とするにはBW≒10kHzなので抵抗値に換算すると、250kΩの熱雑音と等価な値までは許容範囲です。この値は、音量調整VR前の全てのノイズの合計値で満足することが必要でデジタル音源の場合はDAC出力の値と同じですが、アナログ音源の場合は定格出力レベルに対するS/Nが110dB(A)取れていれば十分です。
問題はデジタル機器でのビット落ちによる変調雑音で、広帯域の白色ノイズとは違って「ジュルジュル」と言ったような(言葉で説明しにくいのですが)非常に気になる質の悪いノイズがまとわりつき、レベルは小さくても気になる場合があります。
理論的にデジタルの量子化ノイズは、信号との相関関係が小さい場合はピークが±0.5LSBの3角波になるので0dB正弦波に対する実効値は量子化ビット数がNの場合、6.02N+2(dB)となりCDの16bitでは98.3dBのDレンジの計算ですが、微少信号の場合は無相関にはならずこれより5dB大きなピーク値の変調ノイズが発生します。
16bitで0dB信号が110dBSPLになる再生音量では、この変調雑音は+16.7dBSPLピークなので十分に聞き取れるレベルです。
実際に録音されたCDを再生する場合には、録音その物にある程度の残留ノイズを含んでいるので、これがディザの役目をして量子化ノイズは白色雑音化されて気になることはめったにありません。(CDが出始めの頃は14bit量子化の録音でも実用になっていたのはこの為。)
しかし、ノイズのないクリーンなデータ(テストCDの-60dB信号とか)ではディザによる量子化ノイズ低減がないので、ビット落ちによる変調ノイズをはっきり聞き取ることが出来ます。
16bitのシステムのままでデジタルのみによる音量調整(アンプのゲインは固定)を行なうと、低レベルではビット落ちのノイズがまともに聞こえてしまうのでDACの分解能は少なくとも18bit(ビット落ちのピークで-107dB以下)が必要です。
逆に言えば、録音レベルの管理されている商品音源の再生システムに使うDACの分解能は、20bitあれば最大音量110dB+6dBでもビット落ちのノイズは全く耳に聞こえず、デジタルによる音量調整だけでアナログ的なVRがなくても計算上ではなんら問題ない事になります。(32bitのDACを使用していても、音量調節後の上位20bitデータを送れば十分。元々、DACのDレンジは120dB程度※しかないので、それ以上のデータはノイズレベル以下で意味がない。)
但し、これはDACが理想的に20bit分解能を維持している前提での話であり、現実の素子ではTHD+N=-120dBを満足しないのでデジタルだけの音量調整はアナログに劣るようです。
※世界最高水準DACのモノラルモードで131dBなので、この場合22bitまでは意味がある。
なお、録音機材の場合には、クリップに対するマージンでかなりのビット余裕が必要となるので、生の記録データとしては20bitでは不足で最低限でも24bit必要です。(ミキサーでレベル調整後のラインを記録するなら、24bitでも十分)
●音量調整器でのノイズとDレンジ低下
音量調整器は信号レベルを低下させる役割を持ちますが、同時に抵抗成分からのノイズも発生します。
減衰量が6dBの時が最大となりますが、100kΩ抵抗値のVRを使った場合で25kΩの熱雑音であり、上で検討した信号源で許容できる250kΩより十分小さいので、VR以降の後段のゲインが適切であればノイズの点では問題ないはずです。
しかし、後段のゲインが不適切な場合はシステムのS/Nが低下し、25kΩの熱雑音でも問題となる場合があります。
例として、90dB/Wの8ΩSPKをゲイン+29dB(1.0V定格入力の100Wアンプ)で駆動する場合、プリアンプのVR後のフラットアンプのゲインが+20dBあった場合にはSPK出力音圧が110dBSPLになるVR後の信号レベルは100mVで、VR位置を26dB絞った所(100kΩのVRでは5kΩの出力インピーダンス)での熱雑音はBW=10kHzで0.9μVと信号に対し101dBしかS/Nが取れません。
これは過大なゲインが+20dBもある為で、この場合110dBのS/Nを確保するにはVRの全抵抗値を10kΩに下げて雑音抵抗を小さくする必要があります。
プリアンプのゲインが大き過ぎる場合には、このような現象を避ける為にプリアンプの余分なゲインの分だけメインアンプのゲインを下げる(VR後のフラットアンプ分だけアンプの入力VRを絞る)事で回避できますが、増幅した信号をまた減衰させるのは技術的には非常に無駄な構成です。
(伝達過程で混入したノイズを減少させる意味では伝送レベルを上げる事は役立つが、メインアンプ直前で減衰させる事に意味はない)
●VR以降のノイズ(パワーアンプ以前)
考え方は上の信号源の場合と同じで、パワーアンプ出力でのノイズレベルがAカーブ補正で0.2mV(SPKの能率が90dB/Wの場合)を確保すれば十分。
アンプのゲインが29dBなら、入力換算で-103dB(IHF-A)以下が必要なので、マルチアンプの帯域分割フィルタの残留ノイズはこの値より良くないと前後のノイズも加算されますので無音時にノイズが聞こえてしまいます。
先に検討したように、ホーンシステムをマルチアンプ駆動する場合は、ホーンの能率の分アンプの出力ノイズは下げなければならないので、110dB/WのSPKをドライブするアンプのゲインが29dBなら入力で-123dB(IHF-A)以下が必要です。
パワーアンプ以前の等価ノイズ抵抗は2.5kΩからアンプ内部の雑音分を差し引いた値までしか許容できず、ほとんどの機器は性能を満たしません。
パワーアンプの入力に10kΩのVRが付いているなら、これで信号を1/10に減衰させればシステムとしてのS/Nは確保できますが、入力ATTのないパワーアンプではこれが出来ないので、アンプの手前に外付けATTを挿入必要です。
なお、SPK能率110dB/Wでゲイン29dB条件では、アンプその物のノイズレベルが入力換算で-123dB(IHF-A)ない場合はアンプ以前でどのような対策をしても駄目なので、アンプの出力にSPKネットワーク(ATT)を挿入して音圧を下げなければならなくなります。(ノイズレベルが10dB足りない場合は、100W出力してSPKには10W入るように10dB減衰させる。抵抗では電力が無駄なので、トランス式ATTが望ましい。)
アンプを自作してゲインを自由に設定出来るのであれば、SPKの能率に合わせたゲイン設定にすれば何も問題はなく、技術的にも最もシンプルで無駄がありません。ゲインが+10dBのアンプを作るのはNFB量の関係で逆に難しい部分もありますが、ゲイン固定で定数設定すれば設計は可能です。
メーカー製のアンプの場合、アンプその物のゲイン切替えをするとNFB量が変化して特性が不安定になりやすいので単に入力ATT切替えのみで総合ゲインを変化する物がほとんどです。この場合はATTでゲインを下げてもノイズレベルは改善されません。(入力換算の等価雑音電圧は逆に増加する)
3、その他の性能
●最大スルーレート値(SR)
小信号での周波数特性が100kHzまで伸びていて、10kHzでの歪にも問題がなかったとしても、最大スルーレート値が不十分だと問題が発生する場合があります。
音楽信号を20kHzまでとして、8Ω100W出力では最大スルーレート値は5V/usなので、最低限この値は必要です。(この数値は最大出力に依存する)
→SR値についての解説は、最大スルーレートを考慮した設計法 に記載。
●機械的な安定性
アンプは電気信号しか出力しないので、理論的には機械的な影響はないはずです。メーカー品の場合は落下試験や振動試験をパスする必要があるが、アマの自作では最低限「通常の取り扱い」が出来る範囲での強度さえあれば、簡易的なケースにでも組み込めば問題ないのが普通です。
ところが、実際には機械的な振動は部品にストレスを与え、特にコンデンサでは電極間の距離変化が起電力を発生する(部品がマイクの役目をする)事があり、機械的な安定性は音質に微妙に影響します。半導体のチップも同様で、機械的なストレスは電気特性に影響を与えます。
AM受信機の場合は、受信信号の振幅変化がそのまま検波して出力されるので、内蔵スピーカーからの音圧でハウリングを起こすことがあるほど。
部品の固定方法から、基板の材質、半田の硬さなども微妙に音質に関わってくるのは、これらの現象に起因するのかも知れません。(まだ解明されていない)
高級なアンプがどっしりと重いのは、単に大出力の為に重いトランスを積んでいるだけではなく、シャーシなど構造物にもコストを掛けている為。
但し、何をどうすれば良くなるのかは解明されていないので、これらのノウハウは経験的な音質対策として個人的スキルに任されているのが実態。機構的な音質検討をしたことのない人から見ればオカルト的な内容も沢山ある。
→音質対策についての解説は、音質に関する話(音の不思議) に記載予定。
●安全性
自作レベルでの安全性については、保護回路の設計法 に記載していますが、要するに「人や財産に危害を与えない」事に加えて現代ではEMC(電磁両立性)を満足することが求められています。
さらに、自作品の場合は大目に見られている内容でも、企業として広く販売する場合には守らなければならない法規が沢山存在し、加えて企業内部で取り決められた品質基準も多数存在します。
自作品のメリットとしては、これらの厳しい規制に縛られないので保護の為の余計な部品を付けなくても済む事が挙げられます。(故障したら自分で直す!)
私は長い間企業で品質保証担当をしていたので、部品のMTTFや市場実績から決まる使用基準(ディレーティング規格)や様々な品質試験の基準も知っていますが、具体的な値は守秘義務もあり公表できません。
自作品レベルでの最低限の項目のみ列挙すると、
・部品の最大定格は守る(瞬時値でも)
・半導体の温度上昇は最悪条件時のリード温度で100℃以下
・ケミコンは無負荷時最悪条件で定格以下、抵抗は定格電力の50%(*注)
・1次ヒューズは省略しない
長期使用で真っ先に劣化するのは、
・高温部に近いケミコン
・パターンが100℃近い温度になると半田が再結晶でボロボロに崩れてくる(さらに高温になると基板が茶色に変色してくる)
したがって発熱部品は出来るだけ距離を取り、集中する所は基板に穴を開けるなどの放熱対策が必要です。1W以上の発熱部品はかなり大型のヒートシンクが必須で、半田クラック防止のためにランドを大きくして半田盛りも追加しないと数年で半田が割れる。
*注:抵抗の電力50%ディレーティングは1/4W品までで、1/2W品では30%が無難。1W以上の電力抵抗は同じ基板に乗せる場合、1/4以下の使用率にしないと発熱で他の部品を痛める恐れがある。熱的に分離して放熱条件を整えてやっと定格の1/2まで使える。
オーディオアンプ設計の技術に戻る HOMEに戻る