これまでに、素子自体の基本的な特性の解析と、シングル/差動/SEPPに付いて歪み発生量の定量的な解析を行ない、コンプリメンタリSEPPや共通エミッタ間をバイパスした「新形式セル」について、直線性改善の為の最適化条件を検討しました。
ここではそれ以外の様々な直線性改善手法について、概念と効果をまとめます。(NFBを除く)
・カレントミラーで電流変化を前段に戻しVbe変化を打ち消す手法(スーパーリニアサーキット等)
・Vbe変化を検出して前段に打ち消し電圧を発生させる手法(ZDR、スーパーA等)
・局部NFBでバイアス電圧を制御する手法(トランスリニアバイアス等)
・差動でバイアス電圧をずらして合成gmをリニア化する手法(Multi-tanh方式)
・その他の方式
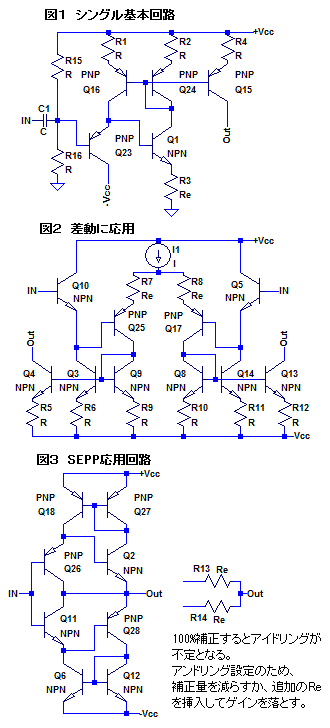
1、カレントミラーで電流変化を前段に戻しVbe変化を打ち消す手法
1980年にパイオニアが「スーパーリニアサーキット」として製品化した技術。
主増幅素子の動作点変動(電流値)を電流のまま前段に戻し、同じ伝達特性を持つ素子にこの電流を流して歪み打ち消し電圧を発生させる手法。
正帰還であり、理想的に補正されると等価的にgm=∞になるので、エミッタ抵抗を局部電流帰還素子として挿入し、gm=1/Reに固定する。
増幅素子としてBi-Trを使った場合は、正帰還された電流がベース電流として入力端子に流入する為、入力インピーダンスは負性抵抗となる。
(通常10kΩ程度の抵抗で終端して安定化する)
歪み発生要因は、打ち消し電圧発生素子の電圧誤差(帰還電流の誤差も含む)が主で、Rg*Ibで発生する入力電流要因も加わる。
Bi-TrではPNP/NPNの特性差が小さいので比較的高精度に打ち消し電圧を発生させることが出来、安定して良好な直線性を得られる。
基本原理回路はシングル動作だが、そのままではReの電圧降下で入出力の電位がGNDからずれてしまい、使いにくい物になる。 (図1で入力にDCカットCを入れているのはこの為。)
定電流回路でQ1のエミッタから直流バイアス電流を引き抜けば入力をGND電位に戻せるが、余計な回路の付加が必要になってしまう。
図2に示す差動回路への応用例では、直流バイアスでの電位ずれの問題が解消される。
さらに、図3のSEPPへの適用も利用価値が高い。(これ以外にも様々な応用形態が考えられる。)
しかし、この回路のままではPP接続で正帰還量を100%にすると、gm=∞の点を相互にショートするのでアイドリングが暴走してしまう
これを防ぐには、補正量を小さくして歪み打ち消しを不完全にするか、追加のReを挿入でアイドリングの暴走を防ぐ必要がある。その結果、A級範囲から外れる時に追加のReで合成gmが曲がり、クロスオーバー歪みが発生してしまう欠点がある。
SEPP接続時のアイドリング不定の問題を解消する工夫が、下の回路である。
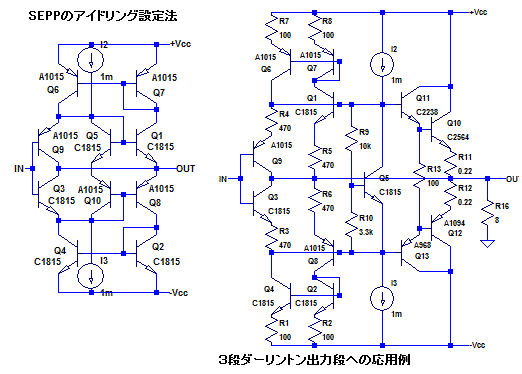
シンプルに、出力石のベース間に通常のバイアス回路を挿入するだけでバイアスは安定する。
これで余計なRe挿入なしに正帰還量を100%にでき、AB級動作でもクロスオーバー歪みは解消される。
あっけないほど簡単に解決しているが、この構成は見たことがないのでひょっとしたら新発明ではないかと思う。(2012/10/01公表)
少し応用すれば右側の図のように普通の3段ダーリントン出力回路(初段がインバーテッドタイプ)に組み込め、動作も安定で非常に大きな効果(無帰還で出力インピーダンス10mΩ以下)が得られる。
なお、厳密には右の応用例は出力段のVbe電圧を検出して前段に戻しているので、SLCではなくて次に説明するZDRの手法に分類される。
2、Vbe変化を検出して前段に打ち消し電圧を発生させる手法(ZDR、スーパーA等)
これは、増幅素子の非直線性(入出力の誤差)を電圧で検出し、これを逆相で入力部へ戻す手法である。
一見NFBと同じようだが、フィードバックするのは出力電圧ではないので、オープンループ制御となる。
(ZDRの原理は上の回路例で示しているので、省略。)
増幅素子に非直線性があっても、逆極性の電圧を加える事で打ち消すのはスーパーリニアサーキットと全く同じであり、検出方法として電流を使うか、直接電圧値から戻すか、の違いのみである。原理的には非常にシンプルだが、電圧検出回路が新たに必要となりやや複雑化する。
可変バイアスのノンスイッチング化手段として知られている「スーパーA」回路も、実は同じ手法を使っている。PPの出力段で双方を歪み打ち消しするとアイドリングが不定となるが、スーパーAではVbeの非線型を利用して電流増大方向のみを補正し、減少方向には作用しないことでアイドリングの安定とB級動作のカットオフ防止を両立している。
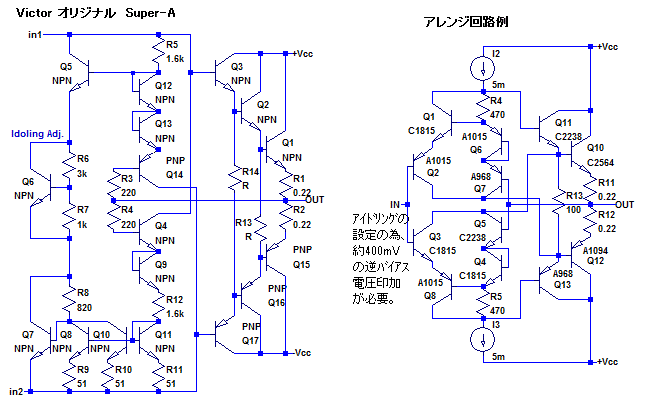
オリジナルのSuper-A回路は、この図のように補正電圧をQ5のB-C間(R5)に発生させている。(負側はカレントミラーで折り返してQ7のB-C間へ)
オリジナル回路ではカットオフ防止効果に主眼が置かれ、バイアス電圧を変調するのみであるので補正電圧が電圧増幅段の出力と干渉し、gmリニアリティ改善の効果は半減する。
右側の図は原回路をアレンジした物であるが、バイアス発生部のVbeをエミッタフォロワに置き換えることで3段ダーリントンの入力を1点に集約し、gmリニアリティ改善効果も狙った物である。
スーパーAでVbe変化をキャンセルすることで入出力電位差が0.2V以下に抑えられる。(小出力時にはVbe補正のゲインが小さいので、クロスオーバー歪みの改善効果は小さく、上の100%補正のようなmΩ単位までの直線化は出来ない)
この回路では初段のバイアス電圧調整がないので、そのままではアイドリング設定が出来ず、アイドリング調整には、NPN-PNPのベース間に逆バイアス電圧を必要とする。
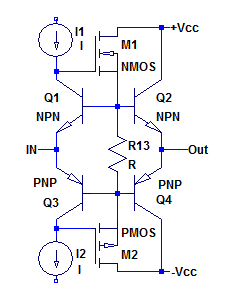
3、局部NFBでバイアス電圧を制御する手法(トランスリニアバイアス等)
「トランスリニアバイアス」の手法は、伝達gmの直線化ではなくてSEPP出力段のバイアス制御方式に属するが、上でスーパーAの話が出て来たので類似の技術として紹介する。
トランスリニア原理が一般的になったのは1990年頃であり、トランスリニアバイアス回路の原型は1990年のハリス社の特許(特開H07-502383)にも見られる。
トランスリニア原理そのものはVbeの指数関数が数珠繋ぎになったループに於て指数関数の加減算=掛算、割算が可能になる性質を利用する物だが、バイアス回路への応用の面では、単にNPN/PNPのバイアス電圧の合計値を一定にするのみである。
エミッタ抵抗が厳密にゼロであれば指数関数関係が保たれるが、実際には素子に数10mΩの内部エミッタ抵抗を含むので、数Aの電流で100mV以上の電圧降下が発生し、トランスリニアの関係は破壊されてしまう。
実用的に有用なのは、右図においてQ1とQ2、Q3とQ4がそれぞれペアとなるレプリカ回路が成立し、安定したバイアスを与える性質である。
例に示した回路では2段ダーリントンのドライバとしてMOS-FET(M1, M2)を使用しており、ゲートとソースの電位差は数V以上あるが、Q1,Q3のC-B局部帰還によりドライバ段の電圧変動はほとんどキャンセルされる。
伝達gmの点では、2段ダーリントンのドライバ段の歪みはキャンセルされるが、出力石の伝達gmはそのままであり、この例ではRe=0の条件のクロスオーバー歪みが残る。
単にバイアス安定化のみを目的とするなら、図のINの点はOPENとして、上下の電流源を電圧増幅段の出力とする回路が利用できる。
4、差動でバイアス電圧をずらして合成gmをリニア化する手法(Multi-tanh方式)
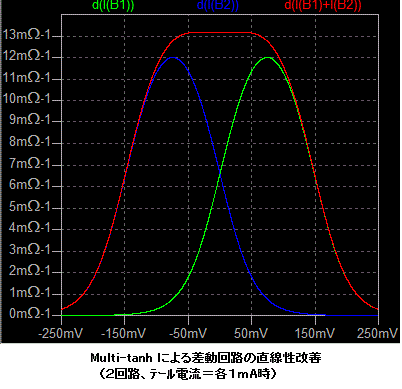 差動増幅回路では、ゼロ点から離れるとどんどんgmが低下するが、複数の差動回路を使ってgmが減少する部分を別の差動のgmが増大する部分で補えばリニアな範囲が拡大できそうである。
差動増幅回路では、ゼロ点から離れるとどんどんgmが低下するが、複数の差動回路を使ってgmが減少する部分を別の差動のgmが増大する部分で補えばリニアな範囲が拡大できそうである。この考え方がMulti-tanh方式であり、Gilbert博士のIEEE1998/1の論文「The Multi-tanh Principle」にその概要が要約されている。(広く知られるようになったのは1970年代の末頃から)
原理的には何個でも横に並べて直線範囲を拡大できるが、普通は2個(Doublet)または3個(Triplet)がよく使われる。
複数の差動のバイアスをずらすのに、外部から電圧を加える方法と、差動のTrのVbe自身に差を持たせる方法がある。Reの挿入なしではTrのエミッタ面積比を4倍に取ると最適のVbe差を発生でき、外部からバイアスを加えなくても自律的に最適条件を保持できる。
最適値のエミッタ抵抗を挿入することで最大平坦化が可能であり、この時のMulti-tanh Doubletのgm特性を右図に示す。gm合成の様子がよく分かる。
Multi-tanhの最適条件を設定するには、外部からバイアス電圧を加えたり、使うBi-Trの特性を変えたりする必要があり、やや使いにくい点がある。
・差動のテール電流を動作振幅に合わせて変調する回路(Multi-tanhの変形)
差動で振幅増大によってgmが低下した時に、共通エミッタ電流(テール電流)を低下した分だけ増加させれば、gmの平坦化が出来るはずである。この考えに基づくのがテール電流を動作振幅に合わせて変調する回路であり、NECの特許(特開H06-303056:信号の二乗でテール電流を変調)などの提案がある。
すでに知られているMulti-tanhの1形態(The Multi-tanh Principleで、three-transistor hybrid formとして記載)は実はこれと同じ動作をしており、3-tale Cellとも呼ばれている。
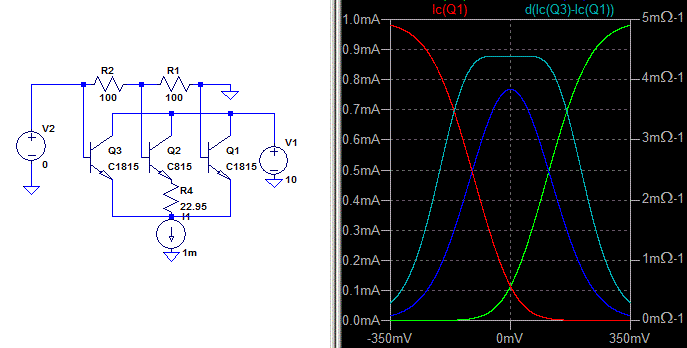
上の図で、テール電流合計は1mA、グラフのIc(Q1)=赤、Ic(Q3)=緑、Ic(Q2)=青であり、Q2のVbeはQ1,Q3より小さく設定され、ゼロバイアスでは0.76mAがQ2に流れている。
入力電圧V2はR1,R2によって等分され、Q2のベースには信号は入力されないがQ1,Q3のVbe変化によってエミッタ電位が変動し、Ic(Q2)は減少する。Q1,Q3で構成される差動回路から見れば共通エミッタ電流はIc(Q2)減少分だけ増加するので、信号振幅の2乗でテール電流を変調する効果が得られる、
その結果として、水色で示すQ1+Q3差動回路のgmは平坦化される。
この3-tale Cellを2つ並べてバイアスをずらし、Multi-tanh動作をさせるのを「Super Multi-tanh」などと命名して特許が出されているが、ここまで来るとさすがにやり過ぎの感がある。
3-tale Cellでは、中央のトランジスタQ2のベースに中点電圧を与え、さらにVbeをずらすか外部バイアスを与えて適切な電流比を設定する必要がある。
すでに説明した「共通エミッタ間にバイパス路を設けた新方式セル」は、この3-tale Cellをコンプリメンタリで積み重ねた物と同等である。従って直線化の原理はMulti-tanhの1形態と見なせる。
だが、単にコンプリメンタリで積み重ねるだけではなく、2Vbeのバイパス路を形成する事で、
・Q2のベース中点電位を作る必要がない(勝手に出来る)
・Q2のVbe調整はバイパス回路をダーリントンとする事でVbeの異なるトランジスタを用意しなくて良い。
つまり、同一特性のトランジスタだけで構成でき、新たなバイアス回路の付加も不要、の効果がある。
非常にシンプルで、かつエレガントな回路であると自負している。
5、その他の様々な方式
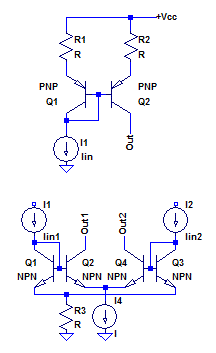
・入力信号をVbe特性に合わせて歪ませる手法
これは、カレントミラーのVbe補正やギルバートセルの電流変換回路にも使われている、最も基本的な直線化の技術であり、有用な手法である。
ZDRでは、歪を含んだ入出力間の電圧差を前段に戻すが、この手法では次段で歪むのを見越して最初に歪み成分を付け加えてから増幅素子に入力電圧を与える。
右のカレントミラーでは、Q1とQ2は一種のレプリカとして働き、入力電流が流れる事で発生するQ1のVbe変化は次のQ2のVbeで吸収され、Q1とQ2のエミッタ電位は等しくなり、結果的にR1,R2に流れる電流は等しくなる。
次のギルバートセルの電流変換回路に使われている回路では、トランスリニア原理によりIc1/Ic3=Ic2/Ic4の関係が常に成立し、出力側の共通エミッタ電流を変えてgmを変調しても出力電流波形は入力電流波形と正確に相似形を保つ。
これらは電流入力なのでgm素子には使えず、アンプ内部の電流伝達要素として使われている。
歪み低減のためには電流で駆動することが必要であり、入力端子には歪ませた電圧が発生するので、電圧で駆動すると歪みが混入し、補正効果がなくなってしまう。
・差動の中央部gm膨らみを、同じ形状の膨らみで打ち消す回路
アイデアとして、差動の中央部のgm曲がりの形状が同じであれば、引算することで歪みを減らせそうである。
実際にその効果を確認したのが次の図である。
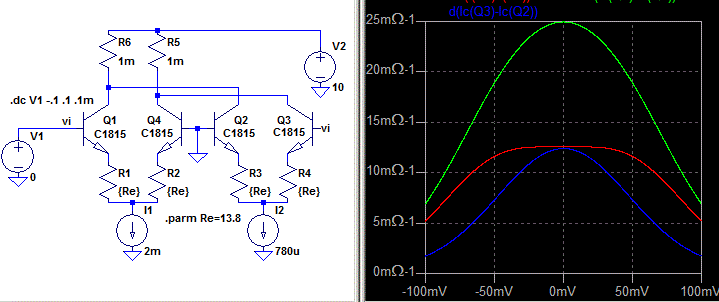
同一特性のトランジスタを使用して同じ値のReを挿入し、適切な値のテール電流差を与えると、この図のようにきれいに平坦化ができる。
(緑が電流の大きい方のgm特性、青が電流の小さい方のgm特性、赤が減算後のgmである。)
実際に、特開H11-177353としてこの原理をアレンジした特許がある。
さらに、特開2008-17058として最近特許が成立しているのにも驚かされる。
確かにリニアリティの改善効果はあるが、gmを減算しているのでテール電流を沢山流している割りには有効利用できる出力電流範囲は狭く、ノイズもさらに増える。スマートとは言いにくい面がある。
・gm変動をRe電流帰還で抑え込む手法
これは、打ち消しではなくてNFBによる改善であり、古来より2段増幅で初段石のエミッタに電流帰還を返す回路として常識的な物である。
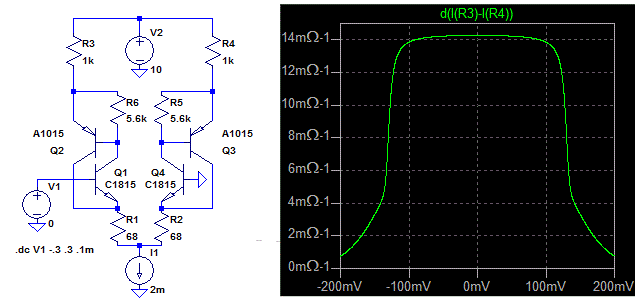
これを差動回路に応用した例がこの図であるが、きれいに平坦化しているように見えて、実はNFBの限界で中央部のgm曲がりは残留している。
2段増幅による局部帰還なので、位相回転が大きくてOPアンプの初段などには応用できない。この部分だけでも使用するトランジスタによっては発振する場合もある。
この回路のアレンジで、特開2002-135065として特許が成立している。(びっくり!)
似たような原理で、単に差動のエミッタ抵抗を大きくして電流を沢山流すと、Reによる電流帰還が掛かるので結果的にgmの平坦化ができる。
がしかし、これは単にゲインを落としているだけであり、同じ出力電流では同じ電流を流したReなしの差動と入力換算の歪みは全く同じである。(必要な入力電圧が増えるので、水増しして薄めているだけ、とも言える。)
AMPの目次に戻る Audioの目次に戻る HOMEに戻る