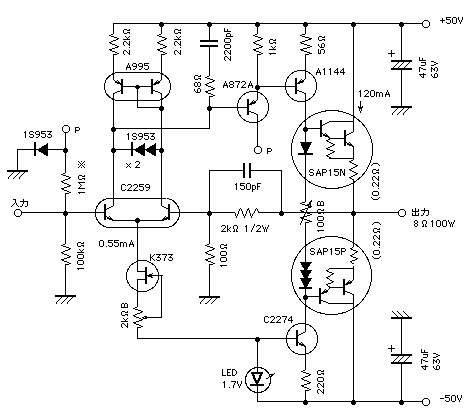 出力段にサンケンの複合ダーリントントランジスタ:SAP15N/SAP15Pを使ったアンプです。
出力段にサンケンの複合ダーリントントランジスタ:SAP15N/SAP15Pを使ったアンプです。基礎設計時の回路のままでは700kHz付近で発振したので、回路(位相補正)を変更しています。
・初段カレントミラー出力の負荷(2200pF)に直列に68Ωを追加
→NFBの進み補償で2ポールの180゜遅れから安定になる範囲まで位相が戻ると踏んでいたのですが、そうは問屋が卸さないようです。
初段負荷はラグリード型の位相補正として、もう一つ進み要素を追加します。
・出力段入力の位相補正ブートストラップは削除
→NFB進み補償のCはA1144のコレクタから戻さなくても、アンプ出力からダイレクトでも良いことが確認できたので、コレクタCと共に削除。
出力のSAP15N/SAP15Pは、入力容量が結構大きめのようです。
・NFB進み補償Cの容量を増加
→元の50pF(100pF2個直列)では、オーバーシュートが大きく、容量負荷時の安定性がない(100kHz方形波入力時にC負荷を入れると発振状態になる)ので容量を増やし、NFB後の-3dBカットオフを500kHzにします。
これで出力に安定化Lを入れなくても、何とか0.1uFまでは耐えられます。
・アイドリングを120mAに増加
→これにより、出力段のクロスオーバー歪みを最小に抑えられます。
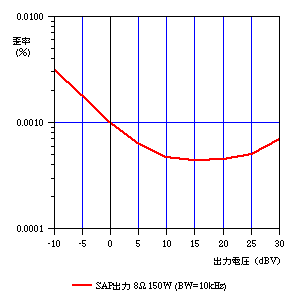
1kHzの歪み率特性(BW=10kHz)は、1W~10Wまで0.0005%以下と、十分な値です。
歪み成分は出力トランジスタのHFE差によるベース電流不揃いによる歪みがほとんどで、今回の例ではNPN側のHFEが小さいために上側の波形が低めに出ました。NPN/PNPのHFEを選別で揃えれば0.0002%程度まで下がると思われます。
BW=10kHzでの残留ノイズは10.5μV、ゲインが21倍ですので入力換算ノイズは0.5μVと、抵抗1.56kΩの熱雑音に等しい値です。信号源抵抗は600ΩATTを600Ωで終端して300Ωですので、NFB100Ω分も差し引くと1160Ωがアンプ由来のノイズ。
BW=100kHzでの残留ノイズは32μVと、計算通り。
カスコード回路もなし、出力段は2段ダーリントンと、前時代的な回路構成ですが、歪み率に関しては立派な物です。
この設計例では、2段目をA872AとA1144のダーリントンにする事で初段の低域ゲインを十分大きくし、トータルのNFB量を非常に大きく(計算上では、1kHzで100dB程のNFB量)することで低歪み化を図っています。
このような多量のNFBを掛けるには、位相補正のテクニック(高域では余分なゲインを捨て、低域では十分なゲインを得る)が重要となります。
この位相補正のテクニック次第で、高域でのNFB量や大振幅での応答性に大きな差がでます。
(この例では、NFBに150pFを入れないでも、A872AのベースとA1144のコレクタ間に47pFを入れるだけで、初段2200pF負荷も削除して安定に動作する)
この後、位相補正の方法の違いによる特性の差を検証して見ます。
なお、このような余計な「テクニック」を弄さずとも、回路の直線性を高める方向(この例で言えば、A872Aのダーリントンをやめて2段目電圧増幅段にカスコードを追加し、出力段は3段ダーリントンまたはMOSを使ったダーリントンとする)で、歪みは簡単に下げられますので、石の数を増やしてでもそのような設計をするのが一般的です。
最初に、位相補正の定数を変更しなければいけなかった理由について検証します。
その為には現実の回路で何が起こっているかを知る必要がありますので、初段から各段の周波数特性を測定してみました。(低域は計算で出るので、100k~10MHzの高周波での実測値のみ)
●初段GM:トランジスタのF特その物と、入力容量によるポール発生の両方が想定されますので、50Ωの
低抵抗で駆動した時と1.5kΩの比較的高インピーダンスで駆動した時の特性を確認、
50Ω(信号源)+100Ω(NFB)駆動時:fc=3.2MHz
1.5kΩ(信号源)+100Ω(NFB)駆動時:fc=2.0MHz
0.25mAでのft=50MHzとして3MHzでのhfeは17で1個当りの入力インピーダンスは1.7kΩ、2個で3.3kΩ。C2259はローノイズTrなのでRbb'が2個で3kΩもあるはずはない(ノイズからも500Ω以下)のですが、1.5kΩを加算してもfcがそれほど下がらないので「実質的」にはRbb'が2個で3kΩ相当の周波数特性となっているようです。
つまり、初段のポールはない物として位相計算をしていたのですが、現実には初段に3.2MHzのポールがありこれをキャンセルする為にもう1個のゼロが必要となったのです。
●2段目GM:こちらはエミッタに56Ωの電流帰還があることもあり、10MHz近くまで問題なく伸びています。
●出力段:ベース入力から出力端までの伝達特性と、入力インピーダンスのF特の2つがありますが、バイポーラトランジスタの2段ダーリントンなので負荷に対して伝達インピーは十分低く、入力インピーのF特が支配的となります。(これが出力端から位相補正のCを戻しても問題ない理由)
出力段の入力インピーF特は、8Ω負荷時に500kHz以下では約50pFの容量性、それ以上では周波数の1.5乗に反比例し、5MHzで100Ωに低下する半負性抵抗となっています。位相にすると135゜回転。純粋な負性抵抗(180゜)には10MHzまでならないのは意外でした。
初段のポールと合わせると1MHzで180゜になり、2ポールでもう一つポールを入れてしまうとNFBのゼロだけでは補正できずに発振するのは当然と言えます。
負荷に0.047uFを入れると配線の浮遊インダクタンス(約0.1uH)とでLC共振を起こし、1MHz付近から急激に位相が回り、1M~2MHzのどこかに大きなピークを持ちます。
この共振点に影響されずにNFBの安定性を保つには、カットオフを500kHz以下にしないと回避できないようです。出力端に安定化用のL(2.2uH程度)を追加すれば、外部のC負荷による急激な位相回りを回避できますので、NFB後のカットオフを1MHz程度にまで上げることが可能になります。
高NFBアンプの位相補正手法について
NFB手法全般については別に整理する頁を設けるとして、ここではNFBを深くした場合の問題点と対策について実際のアンプの特性を例に見てみます。
(今回の例では、位相補正を全て外すと低域での裸ゲインは130dBに達している)
●シンプルな一次補正
一次補正の手法では、比較的低域にポールを1個置き、それ以外のポールを帯域外に追いやらねばなりません。普通は電圧増幅段(二段目)の局部帰還として位相補正のCを置き、これを初段の出力で充電する構成とするので、
GBW=gm/2πCr (gm:初段のGM、Cr:位相補正C)
SR=Io/Cr (Io:初段の最大出力電流)
fc=GBW/Gv、 NFB量=fc/f
したがって、NFB量はfc=1MHzとした場合は1kHzでは60dB止まりのように見えますが、実際には二段目の局部帰還ですでに大きな負帰還が掛かっているので、実質的なNFB量はとても大きくなります。(局部帰還のCを出力端から帰す事ができれば、初段以外の出力段の歪みも含めて帰還が掛かるが、安定度は落ちる)
NFB前の裸のfcは100Hz以下となる計算ですが、NFB後のSTEP応答に裸のfcの低域時定数が現われる事はなく、fc=1MHzでは0.16μsの時定数でNFB後のSTEP応答は収束します。
今回のアンプの例では、初段の実測gm=8ms、Io=0.55mAですので、Cr=47pFとすると、
GBW=8m/6.3/47p=27MHz(Gv=26dBではfc=1.3MHz)、SR=0.55m/47p=11.7V/μs、
fcを下げるためにCr=100pFとするとSR=5.5v/usまで低下してしまいます。この値は20kHzで8Ω100Wをフルスイングするのにやっとで、オーディオアンプとしては不十分な値です。
バイポーラTrの初段ではIo/gmの値が小さいので、シンプルな一次補正では最大SR等の高域特性が出ず、初段の振幅要求や歪みが厳しくなってしまうのが欠点です。補正Cから電源のノイズが流入すると言う点も。
●初段と電圧増幅段を別々に補正し、2次とする手法
今回の設計例のような、2段目にCの局部帰還を掛けない方法です。非常にシンプルな考え方で周波数特性の計算ができ、補正Cでの電源ノイズ除去能力の劣化がなくなるのが利点ですが、クリップからの回復が遅くなりがちな欠点もあります。
簡易的な設計法は、目標とするNFB後のカットオフをfcとして、
Gv=(Rf1+Rf2)/Rf2 (Rf1:NFB抵抗、Rf2:NFBのGND側抵抗)
GBW1=fc=gm1/2πC1 (gm1:初段のGM、C1:初段負荷補正C)
GBW2=fcGv=gm2/2πC2 (gm2:2段目GM、C2:2段目負荷補正C)
fr=fc=1/2πCrRf1 (Cr:NFB補正C)、 1/gm2=Rf2
これで、2次での位相回転180゜からNFBの進み補償で位相を戻し、2次補正で発生するオーバーシュートをNFBのカットオフを使ってキャンセルします。
今回のように、増幅段の負荷以外にポールがあると不安定になるので、必要に応じて初段負荷のC1に直列にRoを追加して位相を戻します。
NFBに進み補償を入れない通常の2次位相補正では、必ずオーバーシュートが発生してNFB後の周波数特性にピークを持ちますが、2次補正のゲインを最大限まで上げてしかもオーバーシュートをキャンセルできるこの手法は、非常に有効だと考えています。(誰かが特許を取っているかどうかは知らない)
これで、fc=1MHzとした場合、10kHzでも80dBのNFB量を確保でき、高域の歪みを低くすることが出来ます。また、低域では初段の振幅が小さくて済む(100kHzでも1次補正の時の1/10)ので、初段の歪みやSR限界を大きく改善できます。
問題点は、初段負荷のC1の値が大きくなる(gm1=10msではC1=1,600pF必要)ので、クリップが発生した場合に2段目入力の電位変化を制限しないと1600pFの電荷を戻すのに初段の出力電流が取られ、回復に時間が掛かります。この点、出力電流が低いバイポーラ初段の場合、特に配慮が必要です。
●電圧増幅段の局部帰還で2次補正をする方法
局部帰還法の必要C容量の小ささと、2次補正の初段に掛かる負担の少なさを両立(良いとこ取り)させるのがこの方法です。電圧増幅段の局部帰還Cを分割し、中点を電圧増幅段の基準電位である+Vccに抵抗で落とします。これにより、2次の補正カーブを実現します。
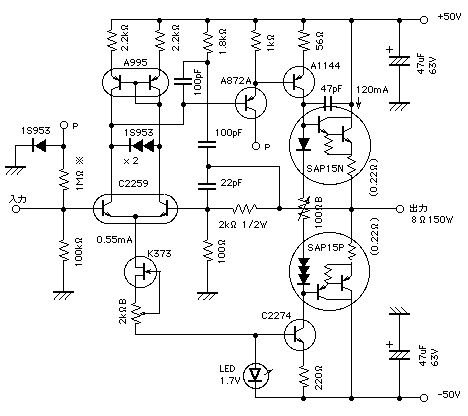
初段負荷に大きな値のCを入れてゲインを殺すのと較べると、裸ゲインは殺さずに局部帰還でゲインをコントロールしているので2段目の入出力インピーダンスが下がり、NFB前の特性も向上します。
実際の回路で定数を検討した結果が、右図です。
変更点は、
・初段負荷の2200pを100pFに
・初段負荷の56Ωを1.8kΩに
・出力端から100pで1.8kへ局部帰還
これで帰還型の2次補正になりますが、その他に
・NFBの150Pを22pFに(初段の3MHzポールをNFB進みで補償)
・電圧段出力に47pF負荷を追加(7MHzでの発振止め)
が必要でした。
2次補正にすることで発生するオーバーシュートをキャンセルする為に、NFBに並列に入れるCはもう少し大きくしたいのですが、この回路の場合は50pFを超えると7MHzで軽く発振する傾向が出るので22pF止まりです。
7MHzという値は、電圧増幅段の出力インピー(約60Ω)と出力ダーリントンの入力インピー(7MHzで60Ω)で発生するカットオフで、出力段の負性インピーダンスでピークを持つのでこの辺りまでNFBのループゲインを高く保つと不安定になります。
出力段とパラに追加した47pFは、この負性抵抗をダンピングする意味もあります。
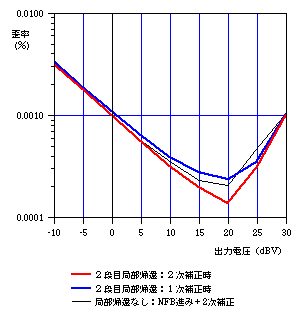
以上の、3つの位相補正方式での1kHzの歪み特性を比較してみました。(実験中に壊したので、出力のSAP15N/SAP15Pは新しい品に交換)
細い黒線は最初の2次補正(局部帰還なし)です。新しい出力石のHFEがたまたま揃ったので10W以下の歪みは良くなりました。大出力では逆にPNP側のHFEが伸びないので急激に悪くなっています。
青いカーブは帰還型1次補正(上の回路図の1.8kΩを削除)です。帰還Cを出力端から戻し、出力段も局部帰還ループに含めていますのでクロスオーバー歪みは抑えられていますが、初段の歪みは2kHzでのNFB量が60dBに満たないのでやや多く出て来ます。
赤いカーブが帰還型2次補正で、10W出力では-117.3dB(0.00014%)と、これまでで最も良い値です。
歪みの点では最良なのですが、パルス応答を見るとやや癖もあります。
【波形写真説明】
下の写真(左)は12W出力(+20dbV)時の歪み波形(BW=10kHz)です。
歪み成分は100dBUP。熱雑音の方が多いので歪み波形は明確には見えませんが、ここからレベルが上がるとPNP側のHFE不足による2次歪みが急激に増加します。
右は1kHzのクリップ波形。上から回復時に変なパルスが出ます。1次補正ではわずかですが、2次補正でNFB量が多くなるとヒゲが結構大振幅となり、この辺りが高NFBの弊害かも
【位相補正方式比較】

●各段個別の2次補正
小振幅ではNFBの進み補償でオーバーシュートをキャンセルしている効果で、500kHzカットオフのきれいなステップ応答。
大振幅では、初段がオーバースイングでカットオフしてしまうので系がリニアでなくなり、2次補正のオーバーシュートが出てしまう。
(PNP側の応答が遅いので、行き過ぎ量が大きい)
●局部帰還型の2次補正
小振幅でもオーバーシュートが発生。(1MHz弱にピークを持つF特)
大振幅ではこの為に行き過ぎ量が増加傾向。
正弦波では、100kHzまではフルスイングでも問題ない。
●局部帰還型の1次補正
非常に素直な1.5MHzカットオフの特性。
小振幅での特性は良いが、最大SRが小さいので右の大振幅応答は厳しい。
計算通りの約10V/μsのSRで、正弦波では50kHzのフルスイングがやっと。
初段にFETを使って数mAの電流を流し、カスコード回路を追加すれば高速性の点では十分な改善ができます。歪みの点でも、実用的にはこれ以上は改善の必要はないレベル(自己満足の世界)ですが、大出力時の歪みの急増(2段ダーリントンのベース電流が原因)を対策すれば、特性的には不満はないはずです。
→改善した設計例を見る
具体的な設計例の解説に戻る オーディオアンプ設計の技術に戻る HOMEに戻る