等価回路によるスピーカー低域特性の解析とキャビネット設計法
ここでは、電気音響理論に基づいて電気入力から音響出力への変換特性を求める方法を解説し、その応用として様々な方式のキャビネットでの特性の出し方(最大平坦特性を基本)について検討します。
参考文献は、(*1):「オーディオ工学」中島平太郎/1973実教出版、(*2):理科年表 ですが、どの教科書を見ても基本的な式は変わらないはず。
―― §1 : 動電(ダイナミック)型SPKの低域等価回路と発生音圧の計算 ―――
●等価回路素子と、関連定数の定義
動電形とは、磁気ギャップ中に可動コイルを置き、電流を流すことにより駆動力を得てコイルを振動させる形式である。(コイルは振動板に直結されているので、直接放射型のスピーカーでは振動板の動きがそのまま空気振動の源となる。)
その動作は電気系、機構系、音響系の3つの要素が密接に関与しているため、それぞれの関連を考慮して解析することで電気信号から音圧への変換特性を計算出来る。(以下、単位系は全てMKSに準ずる)
|
【電気系】 I = (E-e)/(Re+jωLe) :定電圧駆動の場合 |
I:ボイスコイルに流れる電流 (A) E:アンプより入力される駆動電圧 (V) e:ボイスコイルが動くことによる起電力 (V) Re:ボイスコイル及び配線の抵抗 (Ω) Le:ボイスコイルの等価インダクタンス (H) |
|
【機構系】 Vm = (F-f)/(jωMm+Rm+1/jωCm) :振動板は完全剛体であり、これが一定の バネ定数Cmで保持されているモデル |
Vm:ボイスコイルの運動速度 (m/s) F:ボイスコイルに加わる駆動力 (N) f:振動板が空気から受ける力 (N) Mm:振動系質量 (kg) Rm:機械抵抗 (Ns/m) Cm:振動系コンプライアンス (m/N) |
| 【音響系】 P = ZaU |
P:振動板前後面の圧力 (N/m2) Za:振動板前後の音響インピーダンス (Ns/m5) U:空気流量 (m3/s) |
さらに、それぞれの系は以下の結合係数で相互に結合される。
e = BLVm、 F = BLI、 f = PS、 U = VmS
BLは電気系と機構系の相互結合係数であり電磁変換係数(力係数)とも呼ばれる。
B=平均磁束密度(T)、L=ボイスコイル有効長(m)であり、両者の積がBLとなる。
Sは振動板面積(m2)であり、機構系と音響系の結合係数として働く。これらの関係を回路図に書くと、このようになる。
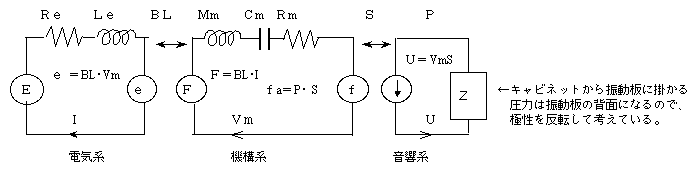
これらの関係式を代入して、機構系の単位に換算してまとめると、このようになる。(主として低域特性を検討するので、Leは無視)
これが動電形SPKの低域基本等価回路である。
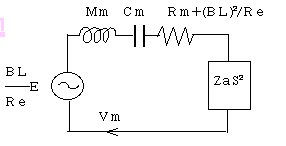 これを解析するには各素子の実際の数値を求める必要があるが、BLやCm、Rmの値を直接測定するのは非常に難しい。
これを解析するには各素子の実際の数値を求める必要があるが、BLやCm、Rmの値を直接測定するのは非常に難しい。従って、比較的容易に測定可能なMm:振動系質量の値を先に求め、振動系の共振周波数foやQの値から等価回路定数を計算で求めることになる。
(Mmを直接求めるにはユニットを壊して振動系を取り出す必要があるため、壊さないで測定するためには既知の質量を振動系に付加し、foの変化量から元のMoを求める方法や、既知の容積を持つ密閉箱に入れてfoの変化量を測定し、Cmを計算で出す方法もあるが、精度は低くなる。)
●スピーカーの電気インピーダンスと、等価回路定数の算出方法
最初の基本式を電気回路のIとEについて解くと、次の式が得られる。
Ze = E/I = Re+jωLe + (BL)2/(ZaS2+jωMm+Rm+1/jωCm)
最初のRe+jωLeの項は、単純にボイスコイル単体の電気インピーダンスである。直流抵抗値から、数kHz以上でインダクタンスによる上昇が発生する。(磁気回路のボールピースに銅キャップをかぶせると、インダクタンスを打消すので高域までフラットなインピーダンスとなる。)
その次の項、(BL)2/(ZaS2+jωMm+Rm+1/jωCm) の部分は、ボイスコイルが磁束中で動いて発電する=逆起電力による物で、動インピーダンスと呼ばれる。これを解析することにより電気インピーダンスから振動系の等価回路素子の値を知ることが出来る。
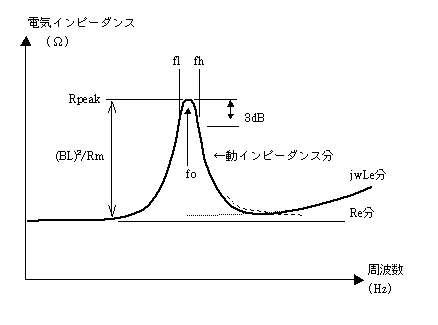 まず、分母のZaS2の項であるが、この値はスピーカーを取り付けたキャビネットによって異なってくる。
まず、分母のZaS2の項であるが、この値はスピーカーを取り付けたキャビネットによって異なってくる。詳細は後に述べるが、スピーカーユニットのfo,Qoを測定するような低い周波数でキャビネットによる背圧が開放型で無視できる場合、ZaS2の値は振動板前後に付加される空気質量のみとなる。
従って、付加される空気質量:Maも含んだ振動板質量をMo=Mm+Maとして考えると、動インピーダンスの値はfo=1/2π√(MoCm)で最大値(BL)2/Rm を取る、LC共振回路の単峰特性となる。 →右図参照。
この動インピーダンス分のQは機械Q(Qm)と呼ばれ、LCR回路であることからQm=(√Mo/√Cm)/Rmで計算されるが、近似的にインピーダンスカーブの最大値から3dB下がる周波数をfl,fhとして、Qm=fo/(fh-fl)で求められる。
→ 下に、正確な計算法の解説あり。
先に機構系にまとめて表した等価回路では、ZaS2の値をMoに組み込むと単なるLCRの直列共振回路になり、LCの値は同じなのでfoは同一だが、抵抗分に関してはRmにBL2/Reが加算されてQが下がる。(これが電磁制動抵抗成分である。)
電磁制動抵抗を含んだトータルのQ(Qo、あるいはQts)は、
Qo =(√Mo/√Cm)/(Rm+BL2/Re) =Qm/(1+BL2/ReRm)
一方、インピーダンスの最大値をRpeakとすると、Rpeak=Re+BL2/Rm、従って、Rpeak/Re=1+BL2/ReRm
これを上の式に代入すると、
Qo =QmRe/Rpeak =fo/(fh-fl)×Re/Rpeak
以上より、Qm,Qoが判明したので、振動板質量が分かればその他の定数は自動的に算出可能となる。
振動板質量Moは、Mo=Mm+Ma (Ma:振動板前後に付加される空気の質量)であるが、空気付加質量は、次の式(*1) で計算できる。
Ma=16ρr3/3
ρ:空気密度=1.2kg/m3
r:実効振動板半径 (m)
【例題1】
ある16cmユニットを平面バッフルに取り付けてインピーダンスを測定し、次の値を得た。
DCR=4.0Ω、Rpeak=20Ω、fo=50.0Hz,fl=45.3Hz,fh=55.3Hz
また、振動系をエッジ、ダンパーの1/2長さで切断して実測した値は次のようであった。
質量=10.0g、振動板(エッジ中央まで)直径=14.0cm
等価回路における、Re,BL,Mo,Rm,Cmと、Qm、Qoの値を計算せよ。
(回答)
まず、 Re=DCR=4
Qm= fo/(fh-fl) =50/(55.3-45.3) =5.0
Qo =QmRe/Rpeak =5×4/20 =1.0
振動板直径=14cmから、r=0.07m、よってMa=16ρr3/3=0.0022kg (2.2g)
従って、Mo=Mm+Ma=0.0122kg (12.2g)
fo=1/2π√(MoCm)より、式を変形すると、Cm=1/(Mo(2πfo)2)
Cm=1/(Mo(2πfo)2) =1/(0.0122*(100π)2) =8.3×10-4 m/N
Rm=(√Mo/√Cm)/Qm =√(14.7)/5 =0.77 Ns/m
Rpeak=Re+BL2/Rmより、
BL=√(Rm(Rpeak-Re)) =√(0.77*16) =3.51 N/A
実際にシステム設計に重要なのは、DCRとfo,Qo,Moであり、BL,Rm,Cmの値そのものは計算しなくても差し支えない。(BLは、ギャップの平均磁束密度とコイルの有効長さ、または電流と発生駆動力から直接求めることも出来る)
なお、キャビネット設計では箱の実容積と対比できるようにユニットの等価コンプライアンスを計算しておくと便利である。
容積Vcの箱に面積Sの振動板を付けた時の箱内空気の振動板に対するコンプライアンスCcは、Cc=Vc/ρc2/S2であるので、
これがユニットの機械コンプライアンスと等価になる容積は、Cm=1/(Mo*(2πfo)2)=Vc/ρc2/S2より、
Vs=ρc2*S2/(Mo(2πfo)2)=(ρc2/4)(r^4/Mofo2) =35400r^4/Mofo2
(但し、c=音速:常温で344m/s、S=振動板面積=πr2)
例題のユニットの場合、Vs=35400*0.074/(0.0122*2500) =0.028m3 =28リットルとなる。
【参考資料】(*2)
物理定数ρ、cの正確な値 (T=温度℃)
空気密度:ρ= 1.293-0.0047T 20℃で1.199 kg/m3
音速 :c= 331.5+0.61T 20℃で343.7 m/s
【解説1】:インピーダンスカーブの-3dBポイント:fl,fh からQmが計算できる理由
LCRの並列共振回路のインピーダンスで、foから-3dB(アドミタンスの実部と虚部が等しくなる)ポイントになる周波数fは、
f/(foQ)=1-(f/fo)2 f/fo=k と置くと、k2+k/Q-1=0
この2次方程式を解くと、
k=(-1/Q±√(4+1/Q2))/2
周波数のマイナス値は正と同じなので、±のマイナス時を反転して両者の差を取ると、
k+-k- =(f+-f-)/fo =1/Q
つまり、Q= fo/(fh-fl) となり、Qが低くても単にfl,fhの周波数の引き算で計算できる。この時 fo=√(fh*fl)
【解説2】:インピーダンスカーブでfoの上昇分が小さい場合の補正
Rpeakの値がDCRよりも20dB(10倍)以上大きい場合は、理論値の-3dBポイントで問題ないが、上昇分が10dBとか、それ以下の場合はDCRの影響で本来-3dBになるはずの周波数で合成のインピーダンスが上昇し、測定される-3dBポイントがずれて結果的に計算されるQoの値が小さくなる現象が発生する。
具体的に、上のQ計算で前提としたLCRの並列共振回路と直列にReを追加した場合の合成インピーダンスを計算すると、本来-3dBとなるはずの周波数での値は、Rpeak比で
Rpeak との比 = √((K2+K+0.5)/(K2+2K+1))
但し、K=Re/(Rpeak-Re) つまり、DCRと増加分の比
| Kの値 | インピーダンス 上昇分(dB) | Rpeakとの比 |
| 0.1 | 21 | 0.710 |
| 0.2 | 16 | 0.717 |
| 0.3 | 13 | 0.726 |
| 0.5 | 10 | 0.745 |
| 1.0 | 6 | 0.791 |
foでのインピーダンスの上昇分が10dBの場合は最大値から-3dB(0.707) ではなくて、0.745倍になる周波数を求める必要がある。
●スピーカーの能率
無限大平面バッフルに取り付けたSPKから発生した音波は、点音源から2π空間に均等に拡散する場合は、
P=(2πfρS/2πL)・Vm 但し、L=音源からの距離(m)、Vm=振動板速度(m/s) (*1)
スピーカーの低域foより上の中音域では、Vmの値が1/fに比例するので音圧は振動板質量と駆動力BLIに依存し、ほぼ一定の値をとる。
Vm=BL*I/2πfMm(Mmは、空気付加質量を含まない、振動系のみの値)
I=E/Ze(Zeは、Reの他に動インピーダンスやLeも含んだ電気抵抗値)
距離Lを1mとすると、
P=EρSBL/2πZeMm ここでS=πr2であるから、 P=Eρr2BL/2ZeMm
【例題2】
例題1のユニットで、中音域の定格インピーダンスが6Ωとして、1W入力時の1m距離の音圧を求めよ。
(回答)
1W入力の条件を入れると、E=√Zeなので、P=ρr2BL/2Mm√Ze
ρ=1.2、r=0.07、BL=3.51、Mm=0.01、√Ze=√6=2.45 を代入すると、
P=1.2*(0.07)2*3.51/(2*0.01*2.45) = 0.42 N/m2
音圧の0dB=0.0002μbar より、1 N/m2 =94dBであるから、
P=20Log(0.42)+94 = 86.5dB
以上のように、再生音圧レベル(dB/W)はBL/√Zeと、r2/Mmの値に比例する。
磁気回路のギャップ内容積Vgは有限であるので、コイルの太さをdとするとL=4Vg/πd2、抵抗Re=L/d2に比例、従ってBL/√Reの値はB√Vgに比例し、磁束密度2とギャップ体積の積(全磁気エネルギー)の√に依存する。
エッジワイズ巻きで導体の有効断面積を大きくすると磁気ギャップの利用率が向上し、同じLでもReを小さくするのに有効である。
なお、磁束を最大限有効に使えるのはボイスコイルの巻幅を磁気回路TOPプレート厚の110%程度にした時だが、それではコイルが動いた時に駆動力BLの値が変動してしまうので歪が大きくなる。
動作振幅範囲での直線性を改善するには、巻幅を上下に余分にはみ出させる方法(ロングボイスコイル)と、磁気回路からはみ出さないまでに巻幅を小さくする方法(ショートボイスコイル)がある。
ロングボイスコイルは重くなるが放熱に有利なので主にフルレンジ~ウーハーに用いられる。ショートボイスコイルはコイルの軽量化が図れるが振幅は取りにくいので主に高域用のユニットに用いられる。
Mmはボイスコイル部と振動板部の合計値であり、コイル部質量に対し振動板が小さい場合は振動板面積を大きくするほどr2/Mmの値が大きくなり能率が向上するが、振動板部分の質量は剛性を保つと半径rのほぼ3乗に比例するので、むやみにrを大きくすると逆にr2/Mmの値が小さくなり、能率が低下する。ボイスコイル部の質量が振動板と同じ程度がバランスが良い。
●指向性と音場特性について
上で説明した音圧の式は、理想的な点音源での値である。実際のスピーカーでは音の波長が振動板半径rに対しC/f=2πr以下では点音源と見なせなくなり、指向性が発生する。具体的には f=C/2r の周波数(38cm口径で約1kHz)で、正面に対し30°方向で-3dB、60°で-10dBになる。
→ 詳しい解説は補足資料の SPKの音圧・指向性の基本原理 を参照
つまり、直接放射型ではf=C/2πr以上では空間に対する音響出力が低下し始めるが、理想的なピストン円板に限定すると、正面軸上に限っては指向性利得が音響出力低下を補いフラットとなる。
平面振動板でない場合は理想的なピストン運動をしていても形状による距離差の干渉で高域ではフラットにならない。
但し、コーンの凹みでF特が乱れるのは38cmユニットでも数kHzの領域であり、振動板自体がピストン運動をしていない場合がほとんどなので無理に凹みを埋めて平面振動板にしても効果はあまりない。
バスレフなどで音源が複数ある場合、ユニット位置と離れていると同様に指向性が発生して「点音源」と見なした計算式とのずれが発生してくる。音波の性質としてr=C/2πfの範囲内なら全ての音源を同一の点音源と見なせ、バスレフの効く周波数は100Hz以下なので距離差が1mまでならさほど気にならないが、ダクト出口までの音道があまり長くなると位相ずれを考慮する必要もある。
なお、音圧の式で「2π空間」と呼称しているのは、無限大平面バフルで区切られた片側の空間を指している。
(点音源から360゜全方向に広がる空間は4π空間であり、完全な無指向性では4π空間全てに均等に音波を放射する。2πとか4πというのは指向角の単位:ステラジアンの値である。)
2π空間では無限大平面バフルで区切られた片側(正面)と、その反対(裏面)に位相が逆の同じ音圧が放射されているが、ここでは正面側のみの音圧を評価している。
振動板の裏側に放射された音圧は、キャビネットにより背面空間が閉ざされた場合に振動板に対する負荷(背圧)となるので、キャビネット設計ではこの影響を計算する必要がある。(後面開放型では背圧は小さいが、前面と背面の音波の干渉を考慮しなければならない。)
実際のキャビネットでは、無限大平面バフル(2π空間)状態は壁面埋込でない限りは有り得ず、有限のバフル面積から背面に回折する影響で低域に関しては4π空間に近い条件となる。
従って、無響室の特性は低域が2π空間で計算した値よりも6dB(半分)に低下し、その低下の度合いはバフルの回折現象(ユニットからの距離に比例した時間差で発生する逆相反射波の影響)で特有の周波数特性を持つ。
(以下、密閉型SPKの解析に続く)
密閉型の設計法に進む スピーカーの理論・設計に戻る AudioのTOPに戻る