5、高分解能歪み率計の設計検討(続き)
5-1、基本ツインTフィルタのノイズ解析
「ツインT」というのは、下の原理図で示すようにCRのT型ネットワークを二つ重ねた形である事からそう呼ばれますが、CRのみで基本波が除去されて基本波の振幅がアンプ部に全く入らない事から、高分解能の歪み測定に有利な方式です。
(ウイーンブリッジやステートバリアブル型などの他の方式では、基本波成分もアンプを通すのでアンプの最大出力や歪みが検出限界に影響する)
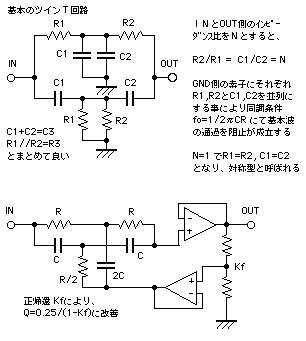
通常は左右のR1,R2とC1,C2の値を同じにした対称型が用いられますが、入力側と出力側のインピーダンス比:Nを大きくした非対称型でも、GNDに繋がる辺に左右辺の素子を並列に挿入する事により同調(基本波の通過を阻止)の成立条件をキープできます。
R1=R、R2=N*R、R3=R1*R2/(R1+R2)
C1=C、C2=C/N、C3=C1+C2
fo=1/(2πCR)
同調のQは、Qo=1/(2+2/N)で、対称型のN=1ではQo=0.25ですがNを十分大きくするとCRのみで実現できる理論限界のQo=0.5に近付けることが出来ます。(ノイズの点では、対称型が最良)
伝達関数は、s=jwf/fo と置いて、
F(w) = (1+s^2)/(1+s^2+s/Qo)
このままではQが低くて基本波以外の
2次高調波も減衰してしまうので、
右の図のように正帰還を掛けてQを
大きくします。
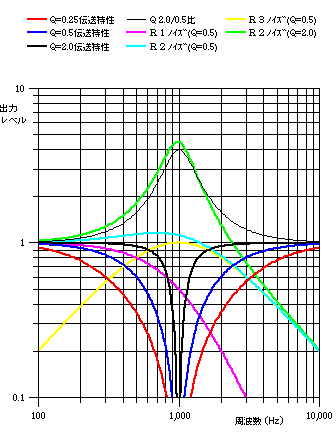
帰還率をKfと置くと、Q=Qo/(1-Kf)
2foでの減衰率は1/√(1+(2/3Q)^2)
Q=2.0とするにはKf=0.875が必要で、この時2foの減衰率は約0.5dBとなります。
右図にQ=0.25:赤、Q=0.5:青、Q=2.0:黒のF特を示します。
Qを上げるほどに1/Qで消去帯域幅が狭くなります。
正帰還率が1に近付くと黒の細線で示すようにfo付近でノイズゲインが1/(1-Kf)で大きくなり、結果的にフィルタの出力ノイズが大きくなります。
N=1の対称型の場合のKf=0.5(Q=0.5)の時に、各辺の抵抗から発生するノイズの出力特性を同じグラフにR1:桃色、R2:水色、R3:黄色で示します。
また、Kf=0.875(Q=2.0)の時のR2のノイズもグラフに緑で示します。
このように、Qを高くするとfo近傍のノイズスペクトルが上昇します。
一方、2fo以上の高域では1/fでノイズゲインが低下するので、BW=10kHzでも100kHzでもツインT部の抵抗から発生するノイズはほとんど増えません。
出力される熱雑音のエネルギーは、5kHz以下の成分が主となります。(fo=1kHzの場合)
先に紹介した自作の1辺16kΩの歪み率計は、Q=2.0なのでBW=10kHz換算での全ノイズ抵抗は23kΩ程度(2段重ねて次段でfo付近のノイズが除去されるのも含み)となり、アンプのノイズも考えると2.0μVの入力換算ノイズはほぼ限界に達しています。
5-2、二次高調波のレベル補正手法比較と最適化
このように、正帰還を掛けてQを上げただけのツインTフィルタでは、2次高調波の減衰量とfo付近のノイズ上昇が相反する関係にあり、しかもQを大きくするとfoでの消去幅が狭くなり、基本波の減衰量が1/(1-Kf)だけ減る欠点があります。
この欠点を回避するために、低Qo時の2foでのレベル低下のみを補正し、fo付近は出来るだけ補正しない手法が考案されています。
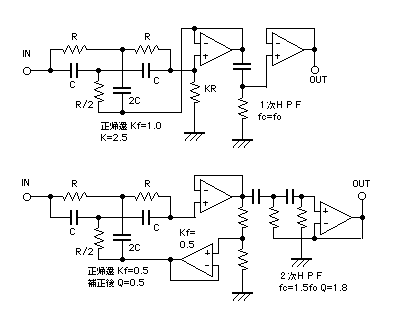
その一つが1984/9月号のラ技に黒田さんが発表している方式で、右図のようにツインT出力を抵抗で終端し、100%の正帰還を掛けると2fo付近の肩特性を上げることが出来、少し持ち上げた特性と1次のCRフィルタの減衰カーブを組み合わせることで2fo付近までフラットに補正する事ができます。
もう一つの方法は、正帰還は小さくしてQ=0.5に止め、2foでのレベル低下をQの高い2次HPFのピークにより補正する方法です。
右の回路のようにfc=1.5, Q=1.8で補正するときれいに2foまでフラットな特性が得られます。
この方式ではQを上げなくて良いので、fo付近のノイズ上昇がありませんし、基本波除去性能の劣化もありません。
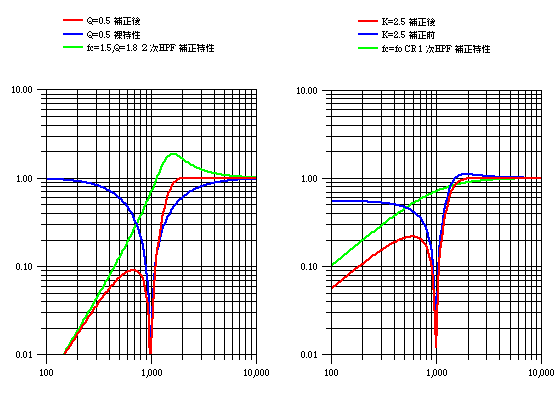
次のグラフ(下の左側)は、2fo付近の様子を拡大比較したもので、緑のQ=2.0のみでは2foで0.5dBの低下があり、2段重ねにすると2次高調波は約1dB小さく測定されてしまいますが、青の1次HPF補正では1段当りの誤差は2foで0.1dB、赤の2次HPF補正では2fo,3fo共にほぼゼロとなります。
右側のグラフは後段のフィルタでfo=1kHz付近の盛り上がったノイズスペクトルを取り除いた後の雑音スペクトルを計算した物です。(全抵抗ノイズの合計値を一辺R比で表示)
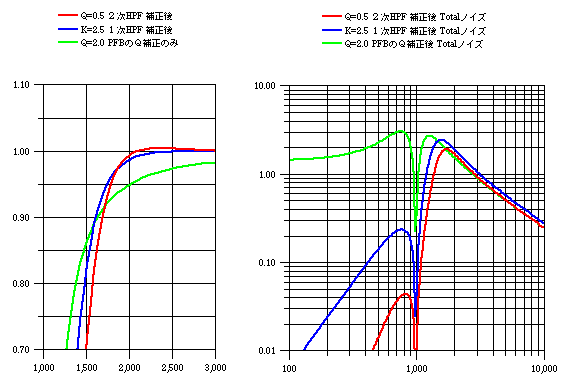
Q=2.0では、ノイズのfoピークは元の4.5倍より低くなりますが、低域ノイズはそのまま出力されます。
HPF補正するとfo以下のノイズはほとんど取り除かれますが、「黒田式」の1次補正では2次補正に較べて中域以上でもノイズゲインはやや大きいことが分かります。
ノイズスペクトルを10kHzまで積分して、全ノイズエネルギーを等価帯域幅で評価すると、
Q=2.5のみ補正なし :BW = 14.5kHz
K=2.5 1次HPF補正:BW = 12.3kHz
Q=0.5 2次HPF補正:BW = 5.9kHz
つまり、最もノイズの少ない2次HPF補正でも、出力ノイズを-133dBv(224nV)とするには一辺の抵抗を530Ω以下にしなければならない事が分かりました。(1次HPF補正の場合では254Ω以下、Q=2.5のみの場合では215Ω以下が必要。)
アンプのノイズも加算されることを考えると、一辺の抵抗はさらに下げる必要があります。
5-3、もっと画期的な手法
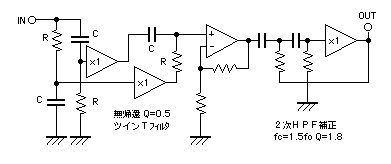
もう一度基本のツインTの回路を良く見ると、CRのみで実現できる最大Q=0.5の場合は R2=∞、C2=1/∞で、C1=C3=C, R1=R3=R (fo=1/2πCR) であり、R2,C2の負荷がぶら下がることによるQの低下がなければ同じ値のCRで入力側とGND側の定数は良いことが分かります。
であれば、この回路のようにバッファで後段を分離すれば、全部同じ値のCRでQ=0.5が実現できます。
Q=0.5ならそのまま2次HPFによる補正で2foフラットになりますので、正帰還Kf=0.5なしでツインTが構成でき、正帰還による+6dBのノイズ上昇をなくすことできます。
正帰還でのQ=0.5の場合は、R+R/2の値の+6dB(ノイズ源抵抗値で4倍)で合計6R相当のノイズですが、無帰還のこの構成では2R相当、つまり1/3のノイズRが期待されます。
先と同様に、各辺のノイズ影響度を10kHzまで積分して後段のフィルタ特性を加味した出力全ノイズエネルギーをRの等価帯域幅で評価すると、
バッファ付き無帰還 Q=0.5 2次HPF補正:BW = 2.27kHz
となり、1/3とまでは行きませんが、劇的にノイズエネルギーを下げることが出来ました。
同じ計算により、1辺の抵抗値が1.37kΩで出力ノイズ-133dBvを実現できるので、抵抗の損失を1Wまでとすると37Vrmsの耐入力となり、ダイレクトにパワーアンプの出力を接続可能となります。(30V入力時のDレンジは160dBに達する)
問題は新たに追加されたバッファアンプで、入力信号に近い大振幅で1kΩ負荷を駆動し、しかも歪み率は-160dBを保つ事が要求されます。これは非常に厳しい仕様ですが、アンプさえ理想的に作れば理論限界値は大きく改善可能。
物量の投入を厭わずにノイズを限界まで下げるには、印加電力が大きくなるのを我慢してとにかく抵抗値を下げることになりますが、1kΩ以下まで下げると許容電力や抵抗の熱歪、大容量Cの歪など難しい問題が出てきます。
抵抗値を出来るだけ下げないでノイズを減らせる”バッファ付き無帰還 Q=0.5ツインT”は、限界性能を上げるキーの技術です。
(なお、ここで説明した「2次HPF補正」は、文献で見掛けた物ではなくて一応flip-flopのオリジナルな方式ですが、調査をした訳ではないので先行例が存在するかは分かりません。「バッファ付き無帰還 Q=0.5ツインT」は、単にCRに同じ値が使えると言う点だけの実用新案がある。)
【参考】:2次高調波のレベル補正手法まとめと性能比較
上で説明した手法以外にも高調波のレベル低下を補正する手法がありますので、周波数特性とノイズ性能を比較表にしました。出力ノイズRはfo=1kHz時の等価帯域、減衰量はfoの調整が0.1%ずれた時の値です。
| 方式 | 出力ノイズR | 2fo偏差 | 3fo偏差 | 減衰量 | 低域F特 | 補正フィルタ特性 |
| 1、Q=0.5のTwinT (0dBバッファ付) を2次HPF補正 | 2.27kHz | +0.04dB | -0.04dB | 64dB | 2次で低下 | 2次HPF Q=2.0 fc=1.45fo |
| 2、Q=0.5のTwinT (kf=0.5帰還)を 2次HPFで補正 | 5.9kHz | -0.06dB | 0.00dB | 64dB | 2次で低下 | 2次HPF Q=1.8 fc=1.5fo |
| 3、K=1.55で終端 (kf=1.0帰還) | 9.8kHz | -0.28dB | +0.28dB | 59.2dB | 7dB低下 | (なし) |
| 4、K=4.2で終端 (kf=0.911帰還) | 10.9kHz | -0.08dB | +0.08dB | 53.8dB | 4dB低下 | (なし) |
| 5、K=2.9で終端 (kf=1.0帰還)を 1次HPFで補正 | 12.3kHz | -0.03dB | -0.01dB | 56.6dB | 6dB +1次低下 | 1次HPF fc= fo |
| 6、Q=0.5のTwinT (kf=0.5帰還)を BPFでfo補正 | 14.4kHz | -0.08dB | +0.08dB | 47.5dB | 通過 | Q=2.0 BPF 加算係数0.67 |
| 7、Q=0.25のTwinT (帰還なし)を BPFでfo補正 | 15.3kHz | -0.08dB | +0.08dB | 45.8dB | 通過 | Q=2.5 BPF 加算係数1.43 |
| 8、Q=2.5のTwinT (kf=0.9帰還) | 14.5kHz | -0.30dB | -0.10dB | 45.8dB | 通過 | (なし) |
| 9、K=5で終端 NFBループ内 Gain=20dB | 43.1kHz (入力換算) | -0.07dB | +0.07dB | 53dB | 4db低下 | (なし) |
(説明)
1: 2次HPF補正方式で補正カーブを微調整。2foをわずかに上昇、3foを下降させる。
2: 2次HPF補正方式の基本説明と同じ。
3: 抵抗終端で1次補正なし。ノイズは低いがF特うねりが大きい。
4: 帰還でのQ補正と抵抗終端の併用。かなり良い特性。
5: 上の説明の1次補正タイプ。少しノイズが多い。
6: Q=0.5でBPFで低下を補償し低域もフラットなタイプ。低域通過分ノイズは不利
7: 低域通過型で帰還Q上げを省略した場合。回路は簡単になるが減衰量がやや劣化。
8: 正帰還で単にQを上げただけの場合。2nd歪成分の減衰が大きい。
9: NFBループ内にツインTを挿入するタイプ。周波数特性は良いがノイズが悪い。
ノイズ的に最良の「1」を初段に使い、比較的フラットな「4」を2段目に使うと、周波数特性のうねりを互いに補正して総合で±0.04dBにできます。
5-4、ツインT部のアンプに要求される性能
最初に説明したように、基本のツインTでは基本波は除去されて歪み成分のみがアンプに入力されます。
基本波の減衰率が60dBあれば30Vrms入力でも振幅は30mVまで低下し、-130dBのTHDを測定するにはツインTを受けるアンプはTHD=-80dBの性能で十分で、アンプ要求性能はとても緩やかです。
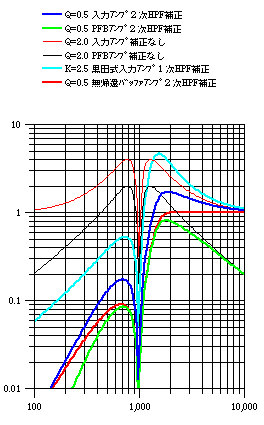
初段アンプで歪み成分を+30dB以上増幅することで後段のノイズはほとんど無視でき、初段入力部のノイズさえ気を付ければ後段はクリップレベルと周波数特性をケアすればOK。
気を付けなければならないのはアンプの入力雑音で、ツインTのRから発生するノイズは高域が低下するので評価全帯域BW=10kHzでも100kHzでもほとんど同じですが、アンプの雑音は高域が低下しないのでBW=100kHzではその分だけノイズは大きくなってしまいます。
右図に示すようにアンプ部のノイズ成分は、正帰還用アンプはR3抵抗と同様に高域が減衰しますが、信号を受ける主アンプは減衰しません。
黒田式の1次補正やQを上げただけのPFB補正では、後段のフィルタで取り除かれる分を差し引いてもfo-2foのノイズが上昇してしまいますが、2次補正では最小限に抑えられます。
例えば、ツインT部の抵抗ノイズを200nVに抑えたとして、BW=10kHzでアンプのノイズを100nV以下にするには、アンプの入力雑音は1.0nV/√Hz、つまり抵抗換算で60Ω以下が必要です。
無帰還バッファ方式では、C側バッファのノイズと主アンプのノイズが全帯域で加算されるので、同じ値にするには各アンプの入力雑音は0.7nV/√Hz、つまり抵抗換算で30Ω以下が必要となります。入力雑音が1.0nV/√HzのOPアンプは入手可能ですが、0.7nV/√Hzはディスクリートで超低雑音のアンプを組まないと実現不可能。
5-5、ウイーンブリッジなど他方式との比較
回路図や特性のグラフは省略しますが、ツインT方式と比較するとウイーンブリッジやザルツァー型などは、一般的に見て
・同調を決めるCRの数が2組で済み、周波数を可変するのに有利。
(ツインTは3組、2次HPF補正すると5組が必要)
・周波数の同調とゼロ点の微調が相互の影響なしにできる。(ツインTは干渉する)
・foを決めるCRは少ないがBainter型以外では信号加算の為のRが余分に必要なので、基本波を除去するための抵抗ノイズが全帯域で大きく、等価ノイズRはツインTより不利
・主アンプに入力信号がほぼ減衰なしで入力され、歪みとDレンジが制限される。
(バッファを使わないツインTではCRの歪まない範囲で最大入力は無制限)
つまり、全自動でオートレンジのような高機能は実現しやすいが、OPアンプを多数使うのでノイズや歪みの限界値は良くありません。
但し、ツインT方式は周波数を可変するのには向いていないので、市販の自動同調型の歪率計はほとんどツインTは使っていない。(THD限界が-120dB程度なのはその為。)
性能限界を決める初段のみツインTを使い、性能はそこそこでよい後段にはBainter型やザルツァー又はウイーンブリッジを使うのも良い選択です。(Bainter型はノイズは良いがCRに印加する信号レベルが高く、CR素子の歪が性能限界となる)
→概要を「ウイーンブリッジ等、他形式のノッチフィルタ」にまとめました。
低歪みOSCの検討に進む AudioのTOPに戻る